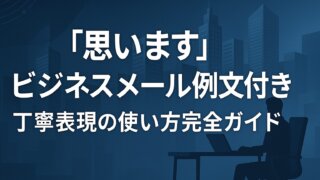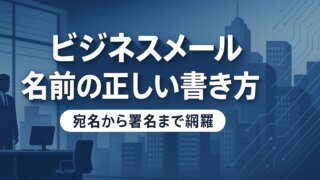ビジネスメールの最後、何を書けば正解なのか悩んだことはありませんか?「名前の書き方はこれでいい?」「“今後とも”はいつ使うべき?」「お礼と感謝ってどう違うの?」──そんな疑問やモヤモヤ、実は多くのビジネスパーソンが抱えているのです。
特に、初対面の相手や取引先へのメールでは、締め方一つで印象が大きく変わります。「最後になりますが」といった定型句も、使いどころを間違えると逆効果になることも。また、名前や署名の書き方、締めの言葉に「ご自愛」を添えるかどうかも、相手との関係性によって判断が必要です。
本記事では、そんな「ビジネスメール最後」の悩みをスッキリ解決!基本マナーから、名前・署名の正しい記載方法、シーン別のお礼表現まで、すぐに使える例文とともに分かりやすく解説しています。メールの終わり方で信頼を得たい方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。
- ビジネスメール最後には敬語と構成マナーが求められる
- 相手との関係性に応じた締め表現が印象を左右する
- 軽い表現や署名の欠如は信頼を損ねる恐れがある
- 場面に合った例文と署名をセットで習得すべきである
【例文付き】ビジネスメール最後の正しい書き方と
![[With example sentences] How to properly write the closing sentence of a business email](https://taishokudaikou-service.com/wp-content/uploads/2025/05/1With-example-sentences-How-to-properly-write-the-closing-sentence-of-a-business-email-640x360.jpg)
- メールの最後に何を書く?|基本マナーを押さえよう
- ビジネスメール最後|名前の正しい記載方法とは
- メール締めの言葉お礼|信頼を得る表現例
- ビジネスメールの締め|感謝を伝える書き方と例文
- メール締めの言葉ご自愛|相手への気遣いを添えるには
- ビジネスメール最後の締め|状況別の定番表現まとめ
メールの最後に何を書く?|基本マナーを押さえよう
ビジネスメールの本文を書き終えたあと、「最後に何を書くべきか」で迷う方も多いのではないでしょうか?メールの締めくくりは、相手に与える印象を左右する重要な部分です。ここでは、メールの最後に書くべき内容やマナーについて丁寧に解説していきます。
まず押さえたい基本構成
ビジネスメールの最後には、以下の3つを意識すると自然な流れになります。
- 感謝の気持ちを伝える
- 今後の対応やアクションを示す
- 結びの言葉で締める
例えば「お忙しいところご確認いただきありがとうございます」「何卒よろしくお願いいたします」などがよく使われます。
結びの言葉には何を使う?
一般的には以下のような言い回しが好まれます。
- 「何卒よろしくお願いいたします」
- 「引き続きよろしくお願いいたします」
- 「ご確認のほどお願い申し上げます」
文面が丁寧であることはもちろん、「お願い」「確認」などの行動を促す内容であることがポイントです。
相手との関係性に合わせた言い回しを
相手が取引先や上司の場合は、より丁寧な表現を心がけましょう。フレンドリーな関係性であっても、ビジネスシーンでは失礼のない言葉選びが求められます。
避けたい表現にも注意
例えば「ではまた」「それでは失礼します」など、軽すぎる締めはビジネスには不向きです。ラフな表現は私的なメールでのみ使うようにしましょう。
メールの最後に「何を書くか」は、ビジネスパーソンとしての信頼にも直結します。常に相手を思いやる姿勢が大切です。
ビジネスメール最後|名前の正しい記載方法とは
メール本文を丁寧に書いても、最後に記載する「名前」が適切でなければ、全体の印象が台無しになってしまうこともあります。ここでは、ビジネスメールの最後に記載する名前の正しい書き方を、例を交えながらご紹介します。
メール署名との違いを理解しよう
「名前の記載」と「署名(シグネチャ)」は似て非なるものです。名前は文章の締めに直接入れるもの、署名はその下に配置される連絡先情報などの付加部分です。混同せず、役割ごとに使い分けましょう。
名前の前に入れる一文の例
名前を記載する直前には、以下のような一文を添えるとスムーズです。
よろしくお願いいたします。
ABC株式会社
営業部
山田 太郎
このように部署や社名を加えることで、相手にとって分かりやすい情報提供になります。
フルネームが原則
ビジネスメールでは、基本的にフルネーム(姓+名)での記載が原則です。ニックネームやイニシャルは、カジュアルすぎてマナー違反と取られかねません。
敬称は不要
メールの最後に自分の名前を書く際、「様」や「さん」などの敬称を付ける必要はありません。敬意を払うべき相手は相手側であり、自分に敬称をつけるのは不自然です。
このような形式を覚えておけば、誰に対しても失礼なくビジネスメールを締めくくることができます。
メール締めの言葉お礼|信頼を得る表現例
ビジネスメールの最後に「お礼の言葉」を添えると、相手への感謝の気持ちが伝わりやすくなり、信頼関係の構築にもつながります。ここでは、実務で使えるお礼の表現と使い方を具体的に解説します。
お礼の表現には種類がある
感謝の言葉にはさまざまな種類があります。目的に応じて適切なフレーズを選ぶのがポイントです。
- 対応へのお礼:「迅速なご対応ありがとうございます」
- 資料送付など:「ご丁寧に資料をお送りいただきありがとうございます」
- 打ち合わせ後:「本日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました」
印象を左右する文末のひとこと
感謝の言葉の後には、次のような一文を添えると丁寧さが際立ちます。
今後とも何卒よろしくお願いいたします。
このフレーズは、感謝だけでなく「今後も関係を続けていきたい」という意志を示す際に有効です。
やり取りの履歴に応じて表現を変える
初回のやり取りと何度も続いているやり取りでは、言葉遣いも微妙に調整が必要です。例えば、継続的なやり取りの場合には「いつもありがとうございます」などの言い回しが自然です。
注意したいこと
「ありがとーございます」「感謝感謝です」などのカジュアルすぎる表現は、業務メールでは控えるべきです。また、長文で感謝を綴るのも読みづらく、要点を押さえた簡潔な表現を意識しましょう。
感謝の言葉は、形式的にならず、具体性と誠意をもって伝えることが大切です。
ビジネスメールの締め|感謝を伝える書き方と例文
ビジネスメールを締める際に「感謝の気持ち」を込めるのは、マナーとしても非常に大切です。単に礼儀というだけでなく、相手との信頼関係を築くうえでも大きな役割を果たします。ここでは、場面別に適した感謝の表現と、その書き方のコツを具体的にご紹介します。
なぜ「感謝」で締めるべきなのか?
メールは文字だけのコミュニケーションであるため、口調や表情が伝わりません。だからこそ、丁寧で思いやりのある言葉づかいが必要になります。特に「ありがとうございました」「感謝申し上げます」などの表現は、読後の印象を和らげる効果があります。
使いやすい例文と場面
以下は、実際のメールで使いやすい締めの文例です。
本日はお忙しい中、ご対応いただき誠にありがとうございました。今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。
注意したいポイント
感謝の言葉も使い方を間違えると、軽く見られたり、不自然に感じられることがあります。例えば「感謝しております」のみでは文が唐突に終わってしまいます。その後に「今後ともよろしくお願いいたします」などの補足が必要です。
上級者向けのひと工夫
相手が特定の支援をしてくれた場合には、その内容を一言入れると、より印象的になります。例えば「迅速なご対応に感謝しております」など、具体性があると誠意が伝わりやすいです。
感謝を込めた締めの言葉は、単なる習慣ではなく、関係性を育てる小さな一歩と考えましょう。
メール締めの言葉ご自愛|相手への気遣いを添えるには
「ご自愛ください」という言葉、最近では少し堅苦しいと感じる方もいるかもしれませんが、ビジネスシーンでは非常に便利で丁寧な表現です。特に季節の変わり目や多忙な相手に対しては、体調を気づかう一文が心に響きます。
「ご自愛」の意味と使い方
「ご自愛ください」とは、相手に対して健康に留意するよう促す丁寧な言い回しです。直訳すると「自分を大切にしてください」という意味合いになります。体調を崩しやすい時期や、相手が忙しそうなときに使うと、気配りが伝わります。
メールに取り入れる自然な例文
以下は、違和感なく使える一文です。
季節の変わり目でございますので、くれぐれもご自愛くださいませ。
相手との関係性に応じた調整がカギ
上司や取引先など、立場が上の方には「ご自愛くださいませ」「くれぐれもお身体にお気をつけて」など、より丁寧な言い回しが望ましいです。一方、同僚など近しい関係であれば、「体調にはお気をつけくださいね」など柔らかい表現でもOKです。
注意点:季節や文脈を意識する
「ご自愛ください」は便利な表現ですが、いつでも使ってよいわけではありません。例えば、真冬や夏の終わりなど、明確な季節感があるときのほうが自然に響きます。
相手を思いやるひと言があるかどうかで、あなたの印象は大きく変わります。
ビジネスメール最後の締め|状況別の定番表現まとめ
ビジネスメールの最後は、シーンや目的に応じて適切な締めの表現を使い分けることが大切です。同じ「よろしくお願いいたします」でも、場面によっては違和感を覚えることも。ここでは、代表的な状況別に分けて定番の表現をご紹介します。
1. お願い・依頼メールの締め
相手に何かをお願いする場合は、丁寧で謙虚な言い回しが基本です。
お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
2. お詫びメールの締め
謝罪の後は、誠意をもって対応する意思を示しましょう。
このたびは誠に申し訳ございませんでした。今後とも、変わらぬご指導を賜りますようお願い申し上げます。
3. アポイント調整時の締め
日程調整メールでは、柔軟性と配慮が重要です。
ご多忙のところ恐縮ですが、何卒ご確認のほどお願い申し上げます。
4. 打ち合わせ後の御礼
会議や打ち合わせの後には、参加に対する感謝をしっかり伝えることが求められます。
本日はお時間をいただき、誠にありがとうございました。
表現に迷ったときの対処法
文例を調べても迷ってしまう場合は、メールの目的と相手の立場を軸に考えると選びやすくなります。形式的な表現でも、「相手を思う気持ち」がこもっていることが伝わるよう心がけましょう。
ビジネスメール最後で差がつく!実践テクニックとNG例
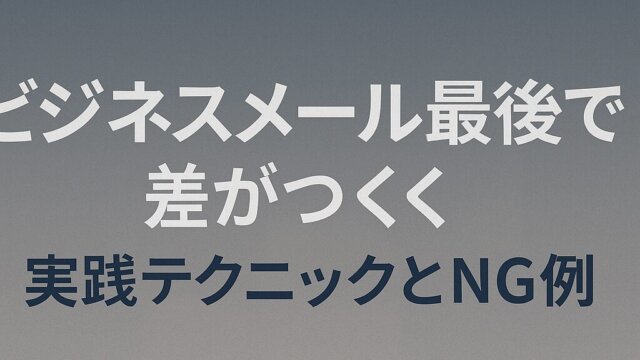
- メール終わりどっち?「以上」「よろしく」の使い分け
- ビジネスメール締め|今後ともを使う場面と例文集
- メール最後署名の書き方|伝わる署名とは?
- 「最後になりますが」メールビジネスでの使い方と注意点
- ビジネスメールの返信の終わらせ方|相手別の実例
- ビジネスメールの終わり方のNG例|逆効果な文面とは
- ビジネスメールの最後を総括
メール終わりどっち?「以上」「よろしく」の使い分け
ビジネスメールの締めで、迷いがちな「以上」と「よろしくお願いいたします」。この2つ、一体どちらを使うべきか、シーンによって適切に使い分けることがとっても大切なんです。
「以上」の使い方とその特徴
「以上」は、報告や説明が終わったことを明確にする言葉です。特に会議資料の送付、業務進捗の報告、調査結果の提示など、情報を一方的に伝える場面にぴったり。
〇〇の件につきまして、下記のとおりご報告いたします。以上、よろしくお願いいたします。
ここでは、「以上」が文の切れ目を作りつつ、「よろしく」で次の行動への期待を添えるパターンが使われています。
「よろしく」の使い方と注意点
「よろしくお願いいたします」は、依頼・確認・感謝の意図を含む万能な締め言葉。ただし、何に対して「よろしく」なのかが曖昧だと、不親切な印象を与えてしまうことも。
例としては、以下のように依頼内容を明記すると親切です。
資料のご確認をお願いいたします。何卒よろしくお願いいたします。
どっちを使う?判断ポイント
- 報告・説明メール:→「以上」で完結
- 依頼・お礼・回答待ち:→「よろしく」
- 両方の意図がある場合:→セットで使用が一般的
どちらもよく使う表現だからこそ、シーン別に的確に使うことで、読み手の印象が大きく変わります。
ビジネスメール締め|今後ともを使う場面と例文集
「今後ともよろしくお願いいたします」──このフレーズ、定型句のように使われがちですが、実は使い方を誤ると形式的で冷たく感じられることもあります。ここでは「今後とも」が持つ意味と、正しい使い方を整理します。
「今後とも」の意味と役割
「今後とも」は、これから先も変わらずお付き合いを続けたいという継続的な関係性の意思表示です。初回のやり取りではなく、ある程度のやり取りがある関係性に向いています。
使用が適切な場面
- 新しい担当者への引き継ぎ連絡
- 商談後のフォローアップ
- 継続案件の途中での連絡
メールでの具体的な使い方
例文はこちら:
今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
注意したい点
「今後とも」を使う際には、その前に関係性の確認や感謝の意を述べてからが自然です。ただ単に締めの言葉として置くだけでは、機械的な印象を与えかねません。
置き換え表現も覚えておこう
やや硬い印象があるときは、「引き続きどうぞよろしくお願いいたします」などに言い換えるのもひとつの手です。
メール最後署名の書き方|伝わる署名とは?
ビジネスメールで見落とされがちなのが「署名」です。単なる名前と連絡先の羅列では、もったいない!署名こそ、あなたの「顔」として機能する大切な要素です。
署名の基本構成
署名には、以下の情報を入れるのが一般的です。
- 氏名
- 会社名・部署名・役職
- 電話番号(直通があれば明記)
- メールアドレス
- 会社住所・URL(必要に応じて)
見やすいレイアウトに整える
読み手が一目で必要な情報を取得できるよう、改行や区切り線を活用しましょう。例を見てみましょう。
株式会社〇〇
営業部 田中太郎
TEL:03-1234-5678
Email:tanaka@example.co.jp
〒100-0000 東京都千代田区〇〇1-2-3
署名で伝える印象づくり
署名は単なる情報ではなく、ブランドイメージを支える一部でもあります。社外向けにはフォーマルに、社内向けや親しい取引先には少し柔らかいトーンでもOK。
注意点とNG例
- 長すぎる署名(スマホで見づらくなります)
- 英語の意味不明なスローガン(説明がなければ逆効果)
- 画像だけの署名(相手のメーラーで表示されないリスク)
署名は自己紹介と名刺を兼ねた情報ブロック。だからこそ見やすく、伝わるデザインが求められます。
「最後になりますが」メールビジネスでの使い方と注意点
「最後になりますが」という表現は、ビジネスメールの締めにおいて丁寧な印象を与える便利なフレーズです。しかし使いどころを間違えると、わざとらしさやくどさを感じさせてしまう恐れも。ここでは適切な場面や注意点を整理していきます。
「最後になりますが」の意味と役割
この言い回しは、話の締めくくりや、本題のあとに伝える補足的な要素を示すために用いられます。メールでは締めの段階に差し掛かっていることを知らせる役割を果たします。
適切な使用シーン
- 長文のメールで感謝や配慮の言葉を述べるとき
- 複数の話題を扱った後に、本題と別の重要事項を伝えるとき
- 目上の相手や初対面の取引先に丁寧な印象を与えたいとき
使用例
最後になりますが、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
注意したいポイント
- メール本文が短いのに使うと、やや大げさに感じられることも
- 毎回同じような文章で終えると、テンプレート的で無機質な印象に
- その後に何か文章が続くと、「最後」が嘘になる可能性もあるので構成に注意
つまり「最後になりますが」は、文章の締めを整えるうえで効果的ですが、場面や文量に応じた自然な使用を心がけたいところです。
ビジネスメールの返信の終わらせ方|相手別の実例
ビジネスメールで返信を終えるとき、相手や状況に応じて適切な締めの表現を選ぶことが、印象を左右します。メールの内容がいくら丁寧でも、締めが曖昧だったり、相手との温度感がズレていたりすると、もったいない結果に繋がりかねません。
取引先(社外)への返信
敬意と丁寧さが必要です。依頼に対する回答や、確認の連絡には以下のようなフレーズが自然です。
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。
社内の上司・同僚への返信
相手の立場に配慮しながら、少しカジュアルダウンしても構いません。
承知いたしました。引き続きよろしくお願いいたします。
感謝を表すとき
指摘や協力への感謝を表す場合、以下のような締めが好印象です。
ご丁寧なご対応、誠にありがとうございます。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
返信が必要ないとき
「ご返信は不要です」といった一言を添えることで、相手の手間を省けます。
取り急ぎご連絡まで。ご返信は不要ですので、どうぞお気遣いなく。
返信メールも立派なコミュニケーション。だからこそ、読み手への思いやりを締めの表現で表すことが大切なんです。
ビジネスメールの終わり方のNG例|逆効果な文面とは
ビジネスメールの終わり方で、マナーを欠いた表現を使ってしまうと、それまで丁寧に書いた内容も台無しに。印象が悪くなるどころか、相手との関係を損ねることもあるので、避けたい表現はしっかり把握しておきましょう。
「以上、よろしく」だけで終える
最もよくあるNG例がこれ。短くて便利に見えるかもしれませんが、相手への配慮がまったく感じられません。
以上、よろしく。
この表現はビジネスにおいてぶっきらぼうで雑な印象を与えるため避けるべきです。
必要以上にカジュアルな表現
例えば、以下のような言い回しは、取引先には不適切です。
じゃ、また連絡しますね!
このような締め方は、プライベート感が強く、信頼性に欠ける印象を持たれます。
回りくどい言い回しや同じ語尾の繰り返し
「~いたします」「~いたします」「~いたします」と同じ語尾が3回続くと、読みにくくくどい印象になります。
全く締めの挨拶がない
本文だけで終わってしまうと、読み手が不安になる可能性があります。特に感謝や期待が含まれていないと、メールが冷たく感じられがちです。
注意すべき点まとめ
- 敬語が適切か再確認する
- 感謝・依頼の気持ちを明示する
- 読み手の立場に合った文体を選ぶ
文面が読み手に与える影響は大きいもの。締めのひと言こそが、メール全体の印象を決めるといっても過言ではありません。
ビジネスメールの最後を総括
- 感謝は最初に伝える
- 締めは敬語と定型で整える
- 依頼には「よろしく」を添える
- 報告文では「以上」で完結する
- フルネームで名前を記載する
- 署名情報は簡潔にまとめる
- 「ご自愛」は時季や関係で使う
- お礼の言葉は文頭または文末
- 「今後とも」は関係維持の意思
- 返信では相手ごとに締めを変える
- メールの文末には余韻を持たせる
- 軽すぎる表現は必ず避ける
- 文末表現の繰り返しは避ける
- テンプレ文でも具体性が大切
- 署名の長さと構造を最適化する
![[Saved Edition] The Complete Guide to Writing the Final Words in a Business Email](https://taishokudaikou-service.com/wp-content/uploads/2025/05/Saved-Edition-The-Complete-Guide-to-Writing-the-Final-Words-in-a-Business-Email-1280x720.jpg)
![[Business email] How would you describe yourself](https://taishokudaikou-service.com/wp-content/uploads/2024/12/Business-email-How-would-you-describe-yourself-640x360.jpg)
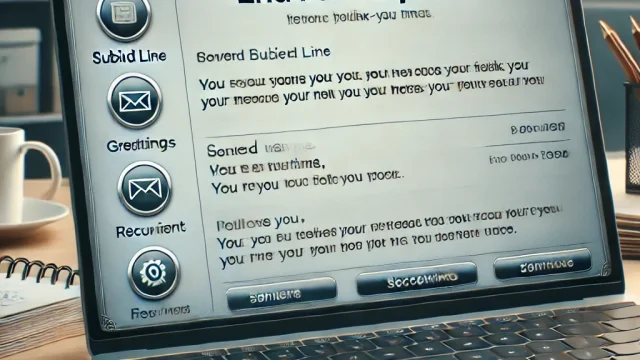
![[Business email] How to use SATE](https://taishokudaikou-service.com/wp-content/uploads/2025/01/Business-email-How-to-use-SATE-640x360.jpg)

![[Business email] As follows](https://taishokudaikou-service.com/wp-content/uploads/2024/12/Business-email-As-follows-640x360.jpg)
![Please let me consult [Business email]](https://taishokudaikou-service.com/wp-content/uploads/2025/02/Please-let-me-consult-Business-email-640x360.jpg)